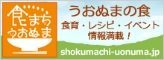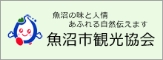2024魚沼市プレミアム
認定品
魚沼の切り菜(きりざい)
(株式会社幸源)細かく刻んだ野沢菜に大根や人参を混ぜ合わせたきりざい。名前の通り「切った野菜」が語源で、雪深い魚沼の冬の保存食として親しまれてきた。かつては数軒あった漬物製造所も今や一軒。創業48年になる幸源が、ふるさとの味を守り、伝えている。



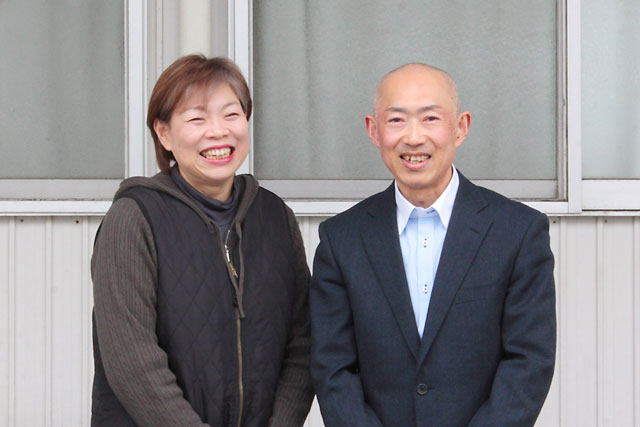
審査員の講評

-
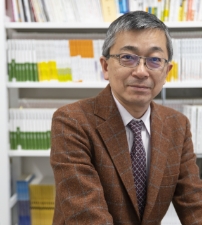
田村 秀 ( たむら しげる )
魚沼の切り菜は魚沼の素材を生かし、魚沼の人に愛され続けたものであり、プレミアム認定に相応しいものだと思います。一方、魚沼市で野沢菜を作る人が減っていることは心配です。魚沼地方に古くから根付いてきたご当地の食であり、これを守り育てていくことはとても大事であり、その意味からもプレミアム認定に合致した産品であることは間違いありません。ラベルなどにももう一工夫が必要だと思いますし、会社の事業規模からいかにして持続的な生産体制を維持するかも課題だと考えます。先行してプレミアム認定された産品の取組みも参考にしてブランド化に努めてください。
-

武藤 麻実子 ( むとう まみこ )
「切り菜」という言葉と魚沼地方に伝わる郷土料理について学びがありました。 当地では給食にも出てくるほどお馴染みだと聞き、県外の自分にとっては非常に興味深い食材だと感じました。よく納豆と混ぜ合わせて食べておられるという点も、「米どころ」である魚沼にふさわしい食材なのではないでしょうか。 魚沼に住む方々にはお漬物を細かく刻んで食することが当たり前すぎて、いわば「名もなき」食べ物・食材というお話もあり、こうした地元に根付く食文化を商品化し、次世代や県外に広めていく姿勢も「魚沼市プレミアム」にふさわしいと思いました。 県内のホテルの朝食などで、色々な人に食べて知ってもらう機会が増えると、なおよさそうです。
-

須田 和博 ( すだ かずひろ )
「魚沼らしさ」って何なのだろう?ということを考えてしまう今回の審査でした。切り菜を和えた納豆は自分が幼かった頃の須田家の食卓にも当たり前に出ていました。堀之内出身の祖母と、小出出身の母が調理する食卓だったから当然だったと思います。ただ、これを「切り菜」と呼ぶことは、今回の審査まで知りませんでした。そこで初めて、納豆にネギではなく切り菜を混ぜるのは魚沼周辺の食文化なのだと知りました。実際に美味しいですし、長野の名物として認知が確立している「野沢菜」も刻めば魚沼の「切り菜」になるわけです。魚沼プレミアムの審査と推奨は、未知なる「魚沼らしさ」を発掘する行為でもあります。それゆえにこそ、認知普及策には納豆に混ぜるのではなく、魚沼産コシヒカリの炊きたてホカホカごはんに、「切り菜」をのせて試食してもらうのが有効なのでは、と思いました。
-

山本 誠 ( やまもと まこと )
長年郷土で愛され続け、家庭に浸透し魚沼では誰もが知る切り菜。原料である野沢菜もご当地では生産者が減少で収穫が年々厳しくなる中で、伝統を継続するために努力されている方々の魚沼への思い。魚沼プレミアム大前提の「魚沼の誇り」を真剣につくり上げていることに感銘しました。また、魚沼産コシヒカリとの相性も抜群であり、コラボしての拡販は将来性を大いに感じます。納豆との組み合わせ、チャーハンや混ぜご飯の具材と多様な調理方法の提案で消費者の関心をより引き付ける潜在性があると感じました。そのような意味合いからも店頭・ECでの販売ルート以外でも外食・中食へのBtoBビジネスなどへも期待が持て、魚沼の地域創生にも十分寄与できると考え認定推薦いたしました。
Special Interview
魚沼の食文化を伝える、
野沢菜由来の漬物
株式会社幸源(こうげん)代表取締役 櫻井 康司さん

細かく刻んだ野沢菜を中心に
1977(昭和52)年、幸源は「ふるさとの味を食卓に」を掲げて創業した。製品の8割を占めるのが野沢菜漬け、そしてこの野沢菜を刻んで野菜と合わせたのが「魚沼の切り菜(きりざい)」だ。10年ほど前「野沢菜が食べられなくなった」、そんなお年寄りの声をきっかけに生まれたという。「きりざいであれば、魚沼の家庭の味を伝えることにもなる」。初代の思いを込めた製品は今、地元の画家が描く魚沼の風景が彩りを添えている。

魚沼の食文化を残したい
そもそもきりざいは、野沢菜漬けの発酵が進んで酸っぱくなる冬、「もう一度おいしく食べられるように」と生まれた郷土食だ。菜っ葉の塩漬けを煮る「煮菜」と同様、雪国ならではの知恵が生かされている。「初代は、魚沼の食文化を残すことにもつながると考えたようです」。二代目の桜井康司さんも、小さい頃からきりざいに親しんできた。大根と人参を加えた製品は「納豆と混ぜ合わせて食べるのが一番おいしい」。貴重なタンパク源も摂取できると重宝されている黄金の組み合わせだ。

味の決め手は煮干し
歯触りを楽しみながら噛んでいると、深いうまみが広がる。味は、初代の桜井文雄さんが考案した野沢菜漬けの調味液が基本になっている。「野沢菜漬けといえば信州。魚沼で作るからには何かひと工夫ほしいと考え、煮干しを思いついたそうです」。山に囲まれた魚沼で魚介とは不思議に思うかもしれないが、かつて魚野川では舟運が盛んに行われ、煮干しや棒鱈が手に入った。「魚沼の切り菜」には、魚沼の歴史も一緒に漬け込まれている。

八海山水系の伏流水を使って
材料の野沢菜は、ほとんどが魚沼産と中魚沼郡津南産だ。一年を通じて製造しているため、冬から春にかけては四国や茨城などから仕入れている。「産地が違えば、香りも歯ごたえも違う。地元産は繊維がしっかりしていて、何より魚沼の水に合う」。幸源では超軟水といわれる八海山水系の伏流水を、野菜の漬け込みから調味液まですべての工程で使用。味付けとして加える醤油は小千谷の山崎醸造製。新潟産を使い続けるため、そして郷土の味を守るため、康司さんは野沢菜農家の後継者育成にも力を入れ始めた。

目指すは魚沼のソウルフード
漬物離れが進む中、「魚沼の切り菜」はファンを増やし、売り上げも右肩上がりになっているという。注目したいのは「子どもが好きだから」と買っていく人が多いこと。「学校給食に取り入れられたことが大きいと思う」。給食では地元の大力納豆(*2023魚沼市プレミアム認定品)とセットで配られ、漬物が苦手な子どもにも人気のメニューになっている。「いつか、子どもたちが思い出すソウルフードになればうれしい」。初代が両親の名前を1字ずつ取って名付けたという「幸源」が届けるふるさとの味と食風景。「食は幸せの源という意味も込められていると思う」と康司さん。思いが食材に、味付けに生きている。
data
◯事業者名 株式会社 幸源(こうげん)
◯所在地 魚沼市十日町360-5(南部工業団地)
◯問い合わせ先 025-792-4780
◯https://uonuma-kougen.com